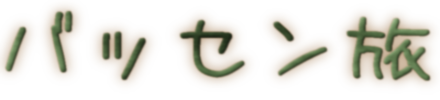つぎに【野球人的ドグマとは?】
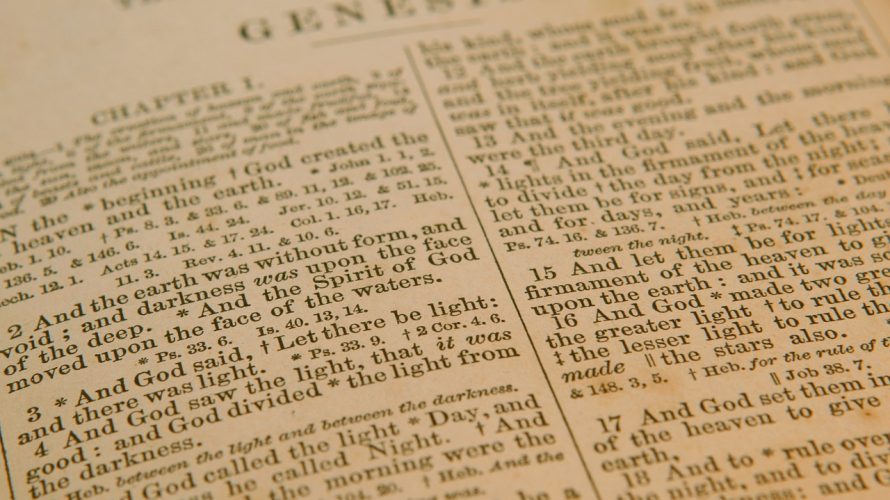
「はじめに」でキレイ目な志を書いたので、汚い志も書いてバランスをとります。
今後このブログでは【野球人的ドグマ】という言葉を頻繁に使います。
これが何を意味するのか?
まず、ドグマとは「宗教上の教義、あるいは独断的・偏見的な説」の事です。
野球界隈には、もはや信仰の類で訂正や否定をするのが困難になってしまった迷信のような言説が多数あります。
それは、野球が日本のスポーツ文化の中で独自の発展を遂げる過程で、野球文化に忍び込み、染みついてしまった【野球人的ドグマ】に原因があると考えます。
野球人が野球を覚えていく際には、ボールの投げ方や、バットの振り方や、基本的な野球のルールなどのOS(オペレーションシステム)を必ずインストールしなければなりません。
ただそのインストール時に、一緒に同梱された「不必要で間違った教えやプログラム」が同時にセットアップされてしまいます。
それは日本の野球文化にプリインストールされてるわけですから、懸命な野球人はその中から脅威となるファイルだけを探し出してアンインストールしなければなりません。
野球が日本でご長寿スポーツ文化として長い間紡いできた功績にはとても価値があると思いますが、一方で伝統的に積み重ねてきてしまった罪過にも目を向けメンテナンスしなければいけないとも思います。
そんな野球文化の功罪を連綿と伝え続けてきたのは、野球人がもつ大衆性に要因があるものとし、その基となる「不必要で間違った教えやプログラム」の事を【野球人的ドグマ】と名付けてレッテルを貼ります。
そしてドグマチックな野球界隈の言説を例にとりながら、それらに批判の言葉を浴びせていく事が目的です。
簡単にいうと、
ご老体となった日本の野球文化にムチを打つ。
アメばっか食ってきた野球文化にムチを打つ。
不必要なモノを排泄できずにいる野球文化にクソぶっかける。
役立たないし間違った説法を説く野球文化にクソぶっかける。
だからある意味このブログは「クソぶっかけブログ」ともいえます。
そのクソをぶっかける照準となるのが【野球人的ドグマ】です。
野球経験者様や野球関係者様であれば自分が信じてきたものにクソをぶっかけられるのは気分が悪いと思いますが、ご安心ください。
私は小学6年生で肩を壊したので力いっぱい思いっきり投げられませんが、コントロールだけは、かなり良いです。
個人的な体験談を具体例としてだすと、私は少年時代、成長も早かった事から同級生の中では身体能力に自信がありました。
少年野球経験者様なら分かると思いますが「足早い・肩強い」同級生に比べて成長が早くて身体能力が高い子ならピッチャーかショートだね、という野球少年あるあるの最前線に居る少年でした。
ですが、その内エースを任される頃には右ひじが悲鳴をあげてきておりました。
それでもコーチ・監督達は何かのお題目のように、
「ひじが下がってるぞ」
「腕が下から出てるぞ」
「下半身で投げろ、手投げになってるぞ」
「弓矢を引くようなイメージで投げろ」
「リリースポイントをなるべく前で放せ」
「耳の横からひじがでてくるように投げろ」
と、肩と腰は水平に横回転、でも腕はなるべく垂直に縦回転で投げ下ろすというような、その時代の【野球人的ドグマ】に適った投球イメージに基づいて、指導という名の日曜日の時間つぶしをしてらっしゃいました。
私も、ひじ肩が痛くならず負担のかからない、それでいて【野球人的ドグマ】に適う模範的なフォームを探しながら、主に90年代に活躍したプロ野球選手を模写しながら、真面目に毎日壁当てをしていました。
しかし、私のひじの痛みは肩へも影響し、結局リトルリーガーショルダーのまま、さらには成長期の原因不明な腰痛にもさいなまれ、野球がつまらなくなり辞めました。
残念ですが、私のトレーニングも私が受けたコーチングも間違っていたと言わざるを得ません。
もう野球はやってませんので、日常生活の中では忘れ去られている事ですが、どこか記憶のかなたにこの原因究明・犯人捜しというテーマが存在していると思います。
ですので、私がクソぶっかける際には、個人的な怨恨がかなり乗っかってますので、同意されない方は適宜差っ引いて読むかして調整してください。
では、日本における野球の起源から現在の日本野球の発展までの私の理解を述べます。
最初にベースボールが日本に上陸したのは米国人の教師が輸入してきた事が始まりとされています。
西暦1871年(明治4年)に東京の開成学校(現東京大学)のホーレス・ウィルソンという米国人教師の方が、教育ツールとして持ってきたらしいですが、そうすると起源からしてベースボールの狙いは躾(=教育)が念頭にあったと考えられます。
そして「野球」と和訳されテレビ・マンガ・アニメというマスメディアを通じて日本国民の大衆的な人気を獲得して日本の超メジャースポーツまで成り上りました。
その過程の太平洋戦時下に、実質上の野球統制令・ベースボール禁止令である「戦時下学徒体育訓練実施要綱」というもので、学生野球は文部省に弾圧を食らった。
その時に学生野球を守ろうとした飛田穂洲氏という方が「学生野球は敵国のベースボール文化ではなく、日本の武道に通じる”野球道”であり、お国の為にも学生に「精神論・根性論(=スポ根)」を注入する事が日本の強さの糧になる」として、学生野球に厳しい鍛錬を抱き合わせる事で、日本の野球文化を守った。
いかにも大日本帝国を想起させる言葉が「野球」にはある。
「犠牲バント」「犠牲フライ」の犠牲打(略して犠打)という名称で、まるで生命をチーム(お国)の為になげうつように表現されて名残りをとどめている。
「送りバント」とも言うのだが、ことさらに身命を捧げるかのような「犠打」という言い方を野球人の【野球人的ドグマ】は好む。
野球を知らない人からしたら、たかだかスポーツで「犠牲」とはやたら物々しく思うが、野球においての犠牲バントの美徳化は、甚だ尋常では無い。
しかし、飛田穂洲氏が日本の野球文化を守るために使ったこのレトリックが、現在も野球人に息づく猛練習・我慢の美徳、ただのパワハラ・不条理な上下関係などの「精神論・根性論=スポ根」の礎になってしまっているので、その飛田穂洲氏が唱えたとされる「野球道」を現代の時代に照らし合わせて、下記のように再定義しましょうよと、桑田真澄氏は論じています。
「練習量の重視」「絶対服従」「精神の鍛練」
↓ ↓ ↓
「練習の質の重視(サイエンス)」「尊重(リスペクト)」「心の調和(バランス)」
時代遅れの野球理論は、革新的なトレーニング理論やフライボール革命などによって瓦解されていく。
そう思っていたが、桑田真澄氏が指摘した旧態依然としたスポ根意識やそれに則した指導方法はそう簡単に根絶やしにはされていない。
それどころか、個々の野球人の心に根を張り【野球人的ドグマ】として我々の判断基準を恒常的に操作している。
日本野球文化のドラスティックな変容が期待できない、のは、日本野球文化の骨格自体が【野球人的ドグマ】でプログラミングされているからだ、とし、日本野球文化の構造を変えないようにプログラムを書き加え(書き換え)ていく、というアプローチでこのブログは進めさせてもらう。
桑田真澄氏が訴えたのが日本野球文化の構造改革だとしたら、このブログは構造改革特区であるといえる。
(いや、やっぱり愉快犯的な破壊衝動に基づいた野球文化に対する横ヤリ、つまりクソぶっかけかな)
2018年5月29日現在タイムリーな話題として「日大アメフト問題」が世間の俎上にのっている。
強めな言い方をすると、私が思うに「スポ根」が深く根を下ろすスポーツ界は、暴行・傷害に類する刑事事件の温床であり、事件として社会に芽を出すには被害届があって初めて発芽するが、スポーツ界の温床には提出されなかった被害届が堆積していて、過去の怨恨が腐って積み重なり腐葉土よろしく養分たっぷりの土壌と化している。
角界の「かわいがり」や度重なる「暴行事件」、レスリングの「パワハラ問題」、ソフトボールやバレーやシンクロなどに代表される鬼コーチの指導、etc、事の顛末は詳しく知らないし知ろうとも思わないが、これらのスポーツはおそらく養分があり余っているのだろうと思われる。
ところで実際の「温床」には養分と水分が必要らしい。
だがスポーツ界の土壌は水分も問題ない。
旧世代のスポ根指導を受けた現代のスポ根指導者により、現役選手に対する「愛情」というカタチで日々十分な水やりがなされている。世代間を飽くことなく連綿とつなぐ最高の温床である。
これは
「スポ根やめますか?それとも スポーツやめますか?」
「野球人的ドグマやめますか?それとも 野球やめますか?」
-
前の記事
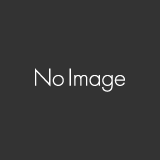
群馬県伊勢崎市 群馬レジャーランド伊勢崎店【HR的あり】 2018.05.31
-
次の記事
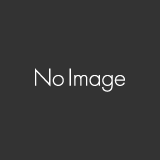
群馬県伊勢崎市 ドリームスタジアムバッティングセンター【HR的あり】 2018.06.03