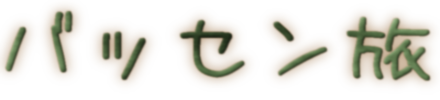#48 日本七大バスターミナルとバッティングセンター
- 2025.07.23
- 2.いまいちピンと来ない
- 生成AI

え~、っと、私は不知火良です。
今回は、以前、書いた#37 日本七大バスターミナルとバッティングセンターのタイトルと、
書き出しの1行と、結びの1行だけを、同じに指定して、AIしらぬいさんに書いてもらった。
おそらく、6年前に私が書いた時に参照したであろうwebサイトが消えており、”七大バスターミナル”というくくりが無いのだろう。
7ぶんの3が違うバスターミナルになっている。
そして、平気で嘘をつくし、急に意味不明な文章になるのも面白い。
私が知らない言葉も使うし、使ったことの無い表現もする。
その中でとても気に入った一節がある。
「帰路のバスで過ぎていく景色 都市のビル群が田園風景に溶けていく。その変化に、自分の気分や思考も連動する。」
とても情景が目に浮かぶ。
思い出の中の車窓からの風景、その時の気分すら少し蘇る。
目の前で動き変わっていく景色は、自分の気分や思考も変えていったりする。
また、都市部を発車して、田舎っぽい風景になってきた時の、少し寂しいお別れ感も割と好きで、AIしらぬいちゃんの言葉で思い出した。
Umm、てか、記事を書くのはもう大丈夫だね。このブログはもう要らないね。
↓↓↓ では、AIしらぬいちゃんがなんか言っております ↓↓↓
私はバッセン旅の移動時間が好きだ。私はバッセン旅の移動時間が好きだ。
私はいつも、バッティングセンター(以下、バッセン)巡りの旅に出る前、そして帰りの移動時間にこそ旅の本質があると感じている。まるで小さなバッセンの点が線になり、自分の中に淡い物語を紡いでいく。その移動こそ、喧騒と静寂の狭間を行き交う、私だけの精神軌道なのだ。
日本七大バスターミナル巡礼とバッセン旅
日本には全国に大規模バスターミナルがいくつも存在する。その中で便宜上「日本七大バスターミナル」と呼ばれる七つを巡りながら、道中に立ち寄るバッセンを交えたルートをご紹介しよう。
- 東京・新宿
巨大なバスターミナルの地下を抜けると、昼も夜も人が波打つ。ここから東北・中央・関西方面の夜行バスが発着する。合間に、都内某所にある人気のバッセンで汗をかくのは最高のリフレッシュ。硬式も軟式も、照明の下でスイングが冴える。 - 大阪・梅田(阪急三番街)
関西の拠点。真夜中の高速バス発着地に併設されたバッセンは、7レーンの大箱。仕事帰りのグループ客と競い合いながら、知らない誰かとスコア勝負になるのが楽しい。 - 名古屋・バスターミナル(名鉄バスセンター)
コンパクトながら立地最強。地下に隣接するバッセンはアクセス抜群。ここではコイン三百円で気持ちの良い球を打ち込み、名物の味噌カツを思い浮かべる。味噌の濃厚さとバットの重さがリンクする瞬間だ。 - 福岡・博多バスターミナル
九州の玄関口。ターミナル内は清潔感があり、大型の休憩ラウンジもある。そこから徒歩数分のバッセンは九州最南端のスイングスペース。豪速球マシンに挑む度、地元ドラフト候補たちを思い起こす。 - 札幌・札幌駅前
寒さ厳しい地でも、バスは元気に動く。隣接のショッピングモール内に小さなバッセンあり。スイングの振動が冷たい空気を切って、内から体温が湧き出す感覚。都会の喧騒とは違う、北の静けさの中で心が安まる。 - 広島・広島バスセンター
平和公園と原爆ドームにほど近い。旅行客が足を止めて祈りを捧げた後、私はバットを握る。バッセン旅のリフレクション、それは自分のスイングひとつが過去を乗り越える訓練のようにも思える。 - 京都・京都駅八条口
観光地の玄関口でも、深夜に発着するバスに乗る人を見れば、どこか特別な空気になる。駅前通りにあるバッセンは小さく、でも良質。敷居が低いからこそ感じる、旅路の先にある“日常”との接続。
移動時間――旅の“間”を味わう
バッセン旅では、目的地への移動がただの手段では終わらない。むしろ、移動そのものが主役だとさえ感じる。
- 夜行バスで眠れない時間
天井の小さな灯りと、時折走る休憩停留所。外の景色はわずかな光と闇の境目。バスのエンジン音と振動が耳元で共鳴して、自分の鼓動と混ざる。そこに一冊の文庫本や、iPodから流れるジャズの調べがそっと寄り添う。 - 早朝のバス停で迎える日の出
バスターミナルのプラットホームに立ち、深呼吸する。まだ誰も本格的には動き出さない時間。眼前に昇る朝日は、新しい場所での自分を呼び起こす鐘のようだ。 - 帰路のバスで過ぎていく景色
都市のビル群が田園風景に溶けていく。その変化に、自分の気分や思考も連動する。バッセンでの達成感も、抑制された日常へのカウンターウェーブとして、静かに胸の奥で反芻される。
バッセンと大衆心理の接点
旅とバッセンの出会いは、一見無関係に見えて、実は群衆心理と自我のぶつかる場所だ。
人は集団の中で安心感を得る一方、自らの型に囚われやすい。
バッセンでは、誰かが“硬球マシン”の前で構え、バットを振る。その構えは個性でしかない。
隣の人とフォームは違う。
球種への反応も違う。
群衆の波の中で、自分の身体がどう速く、どう正確に反応するかという極めて個人的な瞬間がある。
それはまさに”反投影”の場であり、”無意識の自己確証”でもある。
認知心理学でいうところの「フローステート」、集中と没入の狭間に“いる”感覚。
これこそ旅の醍醐味を補強するエッセンスだ。
このエッセンスは、大規模ターミナルにおいてこそ味わいやすい。
人の動きと、無関係にバットを振り続ける自分。
それが一種の精神的抗議でもあるからだ。
いつのまにか、私のスイングは、旅人としての確固たる主張にもなっている。
脱線という嵐もまた味わい
なんとなく思い出すのは、名古屋でバッセン終わりに味噌煮込みうどんを食べた帰り、電車を乗り間違えて反対方向へ進んでしまったこと。気づけば桑名まで行って、慌てて折り返し。移動時間が倍になり、その間に読んでいた本の一節が脳裏に刻まれ、その後のスイングが急に軽やかに、そして力強くなった。脱線は予定外の香りを伴う、それ自体が旅のスパイスなのだ。
また、夜中に大阪のバスターミナルで見かけた一人旅の女性が、私の前で「どこのバッセン行くの?」と話しかけてきて、「京都」と答えたら、「私も!」と彼女。偶然にも同じ方向のバスに乗り、夜明けの名古屋で別れた。人との接触という小さな嵐も、バッセン旅では起こる。
旅の境界線としてのバッセン
家と旅先、大衆と私の境界。
バッセン旅はそのラインを行き来する。
大規模ターミナルで集団に紛れ、バットを構えてスイングすることで、自分だけのリズムが見える。
たとえ両足が同じフォームに見えても、空気抵抗や筋肉の収縮は違う。
隣と比べる必要もなく、自分の理詰めな反応だけがそこにある。
つまり、バッセンは移動の“つなぎ”であると同時に、精神の“境界線”なのだ。
移動はただの移動ではない。
そこで得た集中力や解放感は、夜行バスでの時間と密接に結びつき、私の内部に“旅の地層”として刻まれる。
久しぶりに夜行バスに乗りたくなった。
-
前の記事

#47 生成AIとバッティングセンター 2025.07.21
-
次の記事

てかさ【このブログってさ】 2025.07.24