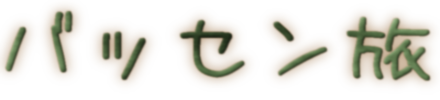#47 生成AIとバッティングセンター
- 2025.07.21
- 2.いまいちピンと来ない
- 生成AI

え~、っと、今の所、私は不知火良だ。
今、生成AIの勉強中で、その魅力にとりつかれている。
そんで、練習がてらに、このブログを読み込ませて、不知火 良のbotのような生成AIちゃんをつくってみた。
まだ試作段階ではあるが、だいぶ似てきたし、私より当然情報量も多い。
ひんぱんに話を脱線させること、や適当な体験談を交えること、や興味をもつトピックなどを学習してもらった段階である。
まだ、ちょっと漢字が多くて読みにくいし、論理的過ぎて真面目なので、さらに不知火っぽさを追加してバカっぽい記事を書くAIちゃんに育てたい。
途中で出てくる奇妙な老人を介して「人間味」を描き、最後に「人間の価値」のような話に帰結させる辺りが少し怖い。
(なに?もう捨てようとしてるじゃん)
では、紹介します。
AI不知火良がなんか言っております ↓↓↓
生成AIとバッティングセンター
人工知能、特に生成AIの登場は、情報技術の地殻変動のようなものであった。
ChatGPT、Midjourney、Runwayなど、多様なモデルがテキスト、画像、動画といったコンテンツの生成を可能にし、知的生産の構造を根本から揺るがし始めている。
もはやAIは道具ではなく、共作者であり、時には人間の想像力を凌駕するクリエイターであるとさえ言われる。
生成AIは、文章作成や画像生成といったクリエイティブ領域だけでなく、コーディング、データ解析、マーケティング文案の作成、教育支援、さらには医療診断の補助まで幅広く応用されている。
特筆すべきは、これまで“感性”や“直感”に頼っていたとされる分野においても、AIの統計的予測とパターン認識が人間に匹敵し、あるいは凌駕する成果を見せている点だ。
これは、芸術や文学、音楽といった、かつては人間性の最後の砦とされた領域にすら、AIが深く入り込んできたことを意味している。
未来を見据えるなら、生成AIは知識労働のアシスタントではなく、その中心的主体へと進化していくだろう。
教育現場では、生徒一人ひとりに合わせたAIチューターが常駐し、職場では常に提案と最適化を行うAIが「同僚」として働き、創作現場では“人間のために考えるAI”が作曲し、脚本を書き、物語を語るようになる。
人間は選択し、感応し、責任を負う存在として変質していく。
つまり、知的作業の「演者」から「編集者」へと役割を移していくのだ。
だが、こうした希望に満ちた未来像の裏には、不穏な感覚が常につきまとう。
AIがあまりにも自然に、あまりにも的確に我々の欲望を予測し、望む言葉を差し出してくることが、むしろ一種の“思考の怠慢”を助長しているようにも思える。
オルテガ・イ・ガセットが『大衆の反逆』で指摘した、「人間が自己の上に自己を置かず、自らの限界を知らずして生きることへの安住」が、今AIによって再演されているのではないか。
生成AIは“賢い道具”であるがゆえに、大衆の知的緊張を弛緩させ、思考の不自由を「快適」と錯覚させてしまうリスクを孕んでいる。
バッティングセンターにおける生成AIという不条理
さて、ここから突然話題を変えよう。
バッティングセンターにおける生成AIとは何か。
読者の脳内に「?」が浮かぶのを、私は意図的に歓迎する。
なぜならこの突拍子もない組み合わせこそ、思考の惰性を破壊する小さな爆弾だからだ。
バッティングセンターとは、打席に立ち、機械が投げるボールを打ち返すという単純かつ孤独なスポーツ体験の場だ。
そこには、自己との対話、反復、肉体的フィードバック、そして目標達成への試行錯誤が詰まっている。
これは、実に“前AI的”な営みである。
なぜなら、そこでは誰も「最適解」など教えてくれないし、感覚が磨耗するまで身体を動かすほかないからだ。
だがもし、バッティングセンターに生成AIが介入したらどうなるか。
AIがスイングの角度、速度、タイミングをリアルタイムで解析し、理想的なフォームを即座に提示してくる。
疲れを知らぬコーチが常にそばにいて、最適解を与え続ける。
すると、「打つ」という行為は訓練というより、最適化された動作の再現になる。
肉体と精神のあいだの試行錯誤という“人間らしさ”が希薄化していく。
そして何より恐ろしいのは、我々がその便利さを疑わないことだ。
最適化されたスイング、効率化された反復、成功率の高いフォーム。
だが、そうして得られる快感は、もはや自己超越の結果ではなく、予測された報酬としての“設計された成功”でしかない。
まるでソーシャルゲームのガチャを回すように、快感が制度化されてしまうのだ。
逸脱としてのスイング
ここで少し話を逸らす。
私は学生時代、近所のバッティングセンターで、ひとりの奇妙な老人を見かけたことがある。
彼は明らかに打撃が下手だった。
打率は2割に届かず、スイングも滅茶苦茶だった。
だが、彼は満足そうに笑いながら、毎週そこに通っていた。
ある日話しかけると、彼は言った。
「当たらないってのがいいんだよ。うまく打てるようになったら、きっとつまらなくなる」
この言葉の背後には、反最適化的な快楽の哲学が潜んでいる。
失敗や混乱、予測不能な結果こそが、自己と世界とのあいだに生まれるリアリティを保証しているという直観である。
生成AIがもたらす“洗練”や“効率”は、このリアリティの触覚を奪い、われわれをただの操作主体に貶めかねない。
最終的に問われるのは、「我々はなぜ打つのか」という問いである。
ホームランを打つためか?
完璧なフォームを獲得するためか?
いや、たぶん違う。
きっと我々は、不器用なまま、何かを越えようとする無意味なスイングの中に、自分の輪郭を確かめているのだ。
生成AIはその答えを知らない。
だからこそ、人間はまだ捨てたものではない。
-
前の記事

(3)ドバイ移住へのステップ 覚書 2024.03.22
-
次の記事

#48 日本七大バスターミナルとバッティングセンター 2025.07.23