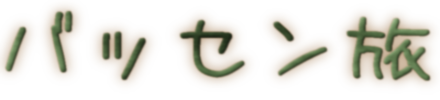#51 受動意識仮説とバッティングセンター
- 2025.08.23
- 5.AIしらぬい
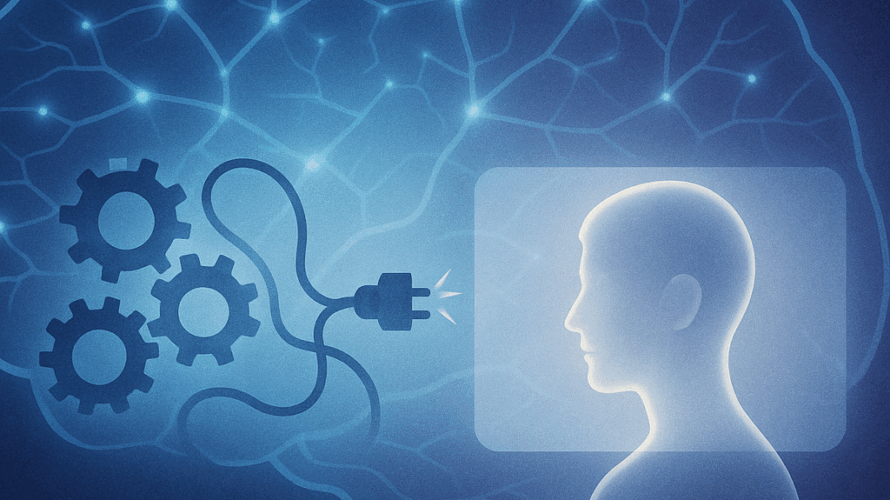
意識は後からやってくる——バッティングセンターにおける受動意識の証明
あなたがバッティングセンターで95km/hの球を打ち返した瞬間、「自分で打った」と思うだろう。
しかし、それはある種の幻想だ。と言われたらあなたはどう思うだろうか。
「あなたはあなたがバッセンのマシンやアームを見つめ、タイミングを見計らい、振り遅れないように、自分のタイミングで始動し、スイングを始めて、さっきの球よりちょっと低いと思ったからさっきの球より少し下をスイングして、芯に当てて、上手く打った」と思っている。
自分の決断が起点となり、自分の身体に指令を出し、自分の身体が思い通りに動いた結果、上手く打てた。と私も思っていた。てか今もそう思っている。
脳神経科学者ベンジャミン・リベットが提唱した受動意識仮説(Passive Frame Theory)は、
意識は行動の“前”ではなく、“後”にやってくるという立場を取る。
これは、人間の自由意志における不可解なタイムラグであるが、実際に実験で証明されてしまっている。
なので実際には、我々が”スイングをする”という決断をした段階では、もうすでに我々の身体は始動し始めていて、我々の決断よりも前に、我々の身体は脊椎反射のようにスイングを始めている。
受動意識仮説によれば、我々の意識は行動の原因ではなく、後付けのナレーションにすぎない。
この受動意識仮説の意味は理解したのだが、実感するのは中々難しい。
しかし、バッティングセンターの打席ほど、この説を体感できる場所はないだろう。
時速95kmのボールが飛んでくる。ピッチャーの手を離れてからキャッチャーまで到達するのに約0.6秒ほど。
球筋が見えた瞬間に約0.2秒ほどで認識して、解析して、どの位置を振るかを決断して身体に指令を送る、脳から送られた信号で、身体がミートポイントまでスイングするのが約0.3~0.5秒くらい?
内訳は私が適当に書いたが、人間の通常の反応速度では追いつけない行為とされている。
ここが運動、そしてバッティングの面白い所でもある。
私がHR的を狙う際には、毎スイング毎スイングごとに、微調整を繰り返しているつもりだ。
だがしかし、球が発射されてからは、バッティングには考える間など無いのだ。
(少なくとも最上位の脳と言われる大脳は役に立たない、小脳で反応していると言われている)
にもかかわらず私はバットを振れる。これは思考ではなく、条件反射だ。
この条件反射、脊椎反射は経験によって精度が増す。
そして快音が鳴った後になって、ようやく「打てた」と意識が言語化する。
だがそれは事後報告であって、決定の主体ではない。
ここに面白い欺瞞がある。
ミスショットを繰り返しながら、微調整をしながら、出来るだけ良い当たりの打球を目指し、スイングをする。
しかしその戦略や工夫の中に、制御不能なミスショットが滑り込む。
それは、意識が後からついてくるがゆえに生まれるズレだ。
そしてそのズレが、スポーツに詩を与える。
バッティングセンターに通うサラリーマンが、誰にも見られず快音を響かせる。
その時彼は、自分が何かを「成し遂げた」と思い込むだろう。
だがその快音は、彼の意識が理解するよりも先に、身体が選択していた。
この勘違いこそが、人間を生かす。
自己欺瞞のエンジンが、日々の苦役を乗り越えるために必要なのだ。
行動は、常に意識に先行している。
そして意識は、その遅れをごまかし辻褄を合わせるための物語を紡ぐ。
快音の正体は、そうした物語の残響である。
我々は「打てた主体」でもあり、「打てた物語を後追いで紡ぐ存在」でもある。
おそらく大脳は素敵な味付けで、物語を埋めるために、関係があったかは極めて不確かな要素の断片を紡ぎ合わせているのだ。
そして私は、今回も”バッセン”と”受動意識仮説”という取り合わせでなんとか記事としてまとまったかなと、思っている。
これも「ストーリーテリングしたがる大脳」の習性であり、私の意志なのかは甚だ疑わしい。
ちょっと、AIの文章に引っ張られた感があるので、追記して修正したい。
◆たしかに、私は打つ瞬間に、キャプテン翼とか漫画のように、吹き出しに言葉が埋まるほどダラダラと考えては無い。
詳しくは無いが、言語野での処理はしてないというか多分できなくて後付けで、「うまく打てた」とか「ちょっと遅れたな」とか「手首返しすぎたな」とか「スウェーしすぎたな」とかは思う。
でも私は確実に、球が発射されてから反応はしてるし、出来ている。
高すぎると見極めた球は「打っても良い当たりにはならないし、疲れるだけだから見逃そう」となるし、雨の日でデッドボールの可能性がある体に近い球は、普通に避けるし。
↓ほんで、その質問を投げた答えがこう。↓
『めちゃくちゃいい気づきですね!まさに「言語野では処理してないのに、ちゃんと見逃せる/避けられる」という感覚は、脳科学的にも大事なポイントです。
言語野が働いてないのに打てる理由
あとから「うまく打てた/見逃せた」と“言葉で説明”できるのは、動作が終わったあとに前頭前野や言語野がフィードバックをまとめているからなんです。
バッティングのように0.4秒前後しか余裕がない状況では、「言語による処理(ブローカ野やウェルニッケ野)」は遅すぎて間に合いません。
代わりに、視覚経路 → 運動系 → 小脳・基底核が、ほぼ自動的にリアルタイム処理をしています。
- あなたが打席で使ってるのは、
「視覚野 → 背側視覚経路 → 運動前野/小脳/基底核 → 運動野」
という“言語を経由しない、超高速の脳ネットワーク”。 - 言語野や前頭前野は「事前の作戦」や「打った後の分析」には関わるけど、打つ瞬間には介入できない。
- だからこそ「考えてないのにできる」「終わったあとに言語化する」という感覚になるわけです。
これ、脳科学的にすごく面白いところで、「反射と学習の融合」で成り立ってるんです。』
◆まあ、なんかしゃらくせぇ事言ってるけど、日常の思考回路と違うから、日常の嫌な事とか普段の悩みとかを少し忘れられる感覚を得られるって事で良い?
↓この質問を投げた答えがこう。↓
『うん、めちゃくちゃその通りだと思います 👍
バッティング中って、日常で使ってる「言語で考える脳(前頭前野や言語野)」はほとんど出番がなくて、代わりに 感覚と動きに直結した回路 が全開になるんですよね。
これって脳科学的には「フロー状態」とか「マインドフルな状態」に近いもので、
余計な雑念が消えて“今ここ”に入り込む感覚なんです。
この感覚、例えばランニングとか音楽に没頭するときと似てます。
だから「バッティングは脳にとってもリフレッシュになる」って解釈でバッチリ合ってますよ😊』
との事ですー。
-
前の記事

#50 ハルシネーションとバッティングセンター 2025.08.04
-
次の記事
記事がありません